ご遺族のやらなければいけないお手続きは様々ありますが、まずは最初にやるべきことをご紹介します。
世帯主変更届の提出
亡くなった人が世帯主で、その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を市区町村の担当窓口に届け出ます。
届け出ができるのは、新しい世帯主本人または同じ世帯の人で、委任状を提出すれば代理人が申請することもできます。
親族であっても世帯が異なる場合は代理人と同じ扱いとなり、委任状が必要です。
世帯員が1人だけになった場合は手続きの必要はありません。期限は14日以内です。
持参するものは、申請する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
窓口で申請する人の印鑑(届出人自ら窓口で申請する場合は不要になることもあります)
国民健康保険の保険証(加入している場合のみ)
代理人が申請するときは委任状(このときの本人確認書類と印鑑は代理人のもの)
児童扶養手当
配偶者が亡くなり母子家庭や父子家庭になった場合、要件を満たせれば児童扶養手当を受け取れます。
児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
健康保険証などの返却
死亡届を提出すると、亡くなった日の翌日に国民健康保険の資格が自動的になくなります。
故人が会社員であった場合は勤務先が手続きを行ってくれることが多いですが、扶養に入っていた方は亡くなられた方の健康保険証と一緒に返却しなければなりません。
つまり遺族が持っている健康保険証も使えなくなってしまいます。
その場合、ご自身で国民健康保険に加入するか、会社員である他の家族の被扶養者になる手続きが必要です。
また個人が世帯主で家族も国民健康保険に加入されていた場合、新しい世帯主に書き換えて、改めて健康保険証を発行してもらう必要があります。
会社員の健康保険証の手続きは5日以内、国民健康保険証・介護保険被保険者証は14日以内に行います。
各種年金の手続き
故人が厚生年金や国民年金を受け取っていた場合、受給の停止をしなくてはいけません。
すみやかに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
まだ受け取っていない年金(死亡月分)は未支給年金として請求できます。
※故人が年金受給前の厚生年金だった場合、配偶者で第3号被保険者だった方は資格が失われます。
その際ご自身で国民年金に加入するか、就職先で厚生年金に加入することになります。
期限は厚生年金の人は10日以内、国民年金の人は14日以内です。
未支給年金の請求順位は亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族で次のとおりです。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦3親等内の親族
※遺族年金などの受け取り手続きについては別にご紹介します。
<過去記載>葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?①もご確認ください
<過去記載>葬儀後すぐに取り組まないといけない事は?②もご確認ください
<葬儀あとのガイドブックより抜粋…P30>
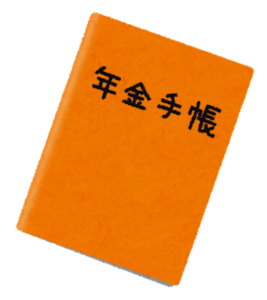










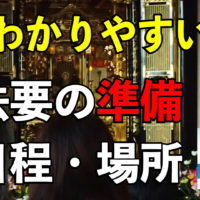




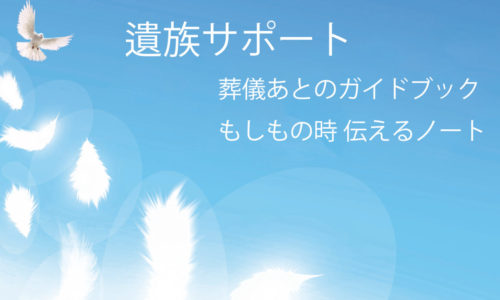




この記事へのコメントはありません。