相続が発生した時に、単純相続をするのか? 相続の放棄をするのか? 選択しなければいけませんが、3つ目の方法「限定承認」についてご説明します。
限定承認とは
相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産の債務を支払い、債務が多くても自己の財産を使って弁済する必要がなく、財産が残れば相続できるのが限定承認です。
つまり相続財産の中で借金があればそれを清算し、プラスになれば受け取る事が出来て、マイナスになった場合は相続人がその責任を負うことはないという制度です。
相続財産がプラスになるかマイナスになるかわからないときに使える都合のいい制度ですが、それを使うには条件があります。
まず、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し出なければなりません。
限定承認は相続放棄と違って、単独ではできません。
相続人全員で限定承認の申し出をすることになります。
従って、相続人が複数いる場合に1人でも限定承認を認めななければ限定承認はできません。
限定承認の3つのケース
①債務超過であることが分かっている場合
②負債の額が不明確なので、法律手続きで明確にしてプラスの財産を相続したい場合
③プラスとマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いか判断がつかない場合 など
限定承認は家庭裁判所への申立てが複雑なほか、準確定申告や譲渡所得税の申告が必要になる場合が殆どで、費用もかかったりします。
限定承認において資産を売却した場合には、みなし譲渡所得税を負担しなければならないこともあります。
このように安易に限定承認を選択すると,思わぬ負担を背負う可能性があります。
限定承認を選択するかどうかは、できる限り相続財産を調査し手間や費用の負担を考慮しつつ検討しましょう。
実際にはこの限定承認の方法をとることは、さほど多くはありません。
やはり、相続放棄に比べると手続きが複雑であり、相続人が単独で単純承認や相続放棄をしてしまうと利用できなくなってしまうからです。
相続人全員の足並みが揃わないと利用できない面も、制度利用の難しさになっていると思います。
限定承認のやり方
限定承認は,相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った時から3か月以内に行わなければならないのが原則です。
3か月を超えると法定単純承認が成立し、利用できなくなってしまう事は相続放棄と一緒です。
ただし期間を延長してもらうため、亡くなった方の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて期間の延長を認められる場合もあります。
限定承認をするためには,家庭裁判所に「限定承認の申述書」に戸籍謄本や被相続人の除籍謄本,財産・負債に関する資料など一定の書類を添付し提出します。
後日、内容等に不明点があるような場合には、問い合わせや資料の追完などが求められることもあります。
これらの照会に回答するなどした後、裁判所によって限定承認の申述を受理するか否かの判断がなされ、受理されれば限定承認受理について通知書が送られてきます。
通知書が届いたならば、すみやかに相続財産の清算手続きを始めなければいけません。
このように限定承認は手間がかかるものですが、検討される場合には専門家を使った方がスムーズに行えるかもしれません。
そういう時は、一度相談されてはいかがでしょうか。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P50>
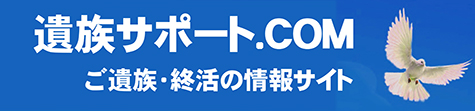









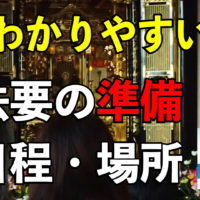









この記事へのコメントはありません。