相続人になるかどうかの分かりにくいケースをまとめてみました。
○胎児
相続開始時はまだ生まれていない胎児は、生まれたものとみなされ相続権があります。
ただし、死産であった場合は相続人にはなれません。
通常、胎児には権利能力は認められていませんが、相続に関する権利能力は例外的に、胎児にも認めると民法886条で定められています。
胎児の身体が母体から生まれて、少しでも生きていた場合は相続権が認められるのです。
胎児については特別代理人の選任が必要です。
また、民法と税法では胎児の扱いが異なり、相続税の申告の際には、胎児は除外して考えます。
○非摘出子
婚姻関係のない男女の子ですが、母親との間は親子関係が生じます。
父親とは「認知」が必要であり、認知された非摘出子だけが相続人になります。
○養子
養子は実子と全く同じに扱われ当然に相続人になり、また実親の相続人にもなります。
ただし、特別養子(実親と親族関係が終了する養子)は実親の相続人にはなれません。
○離婚した元配偶者と子
元配偶者は他人なので相続人ではありません。
しかし子は元配偶者が引き取っていても相続権があります。
(婚姻時に元配偶者の連れ子であった場合は、養子縁組をしていなければ相続権はありません)
○再婚した配偶者と連れ子
配偶者は相続人ですが、連れ子は養子縁組をしないと親族関係は無く、相続人ではありません。
(養子縁組をしてると相続権があります)
○内縁の妻や夫
相続人にはなりません。
○事実上、離婚状態の配偶者
相続人になります。
○子の配偶者
たとえば、息子の嫁が義理の親(夫の親)に尽くし、介護などのお世話をいくらしていても相続人にはなれません。
相続人になるために、養子縁組をする方法があります。
養子縁組をしても実家の親との親子関係は変わらず、嫁ぎ先と実家と両方で相続人になれます。
いかがでしょうか?
今まで書いたものもありますが、ここでまとめてみました。
いずれにせよ、実態ではなくどう国に届けられているかがポイントになります。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P47>








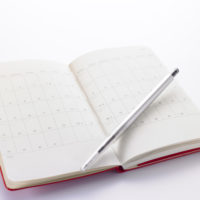


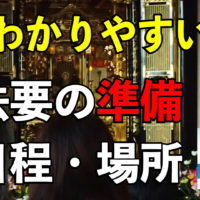









この記事へのコメントはありません。