遺言書を見つけても開封してはいけない
「自筆証書遺言」を見つけて、封筒に封印があった場合、すぐに開封してはいけません。
封印がないときは開封して中を見てもよいですが、できるだけ遺族が集まっているときがいいでしょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度を使って保管されている遺言書以外の遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
封印されていない遺言書も同様です。
検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認することで、遺言書は裁判官によって開封されます。
これにより偽造や変造などの不正を防ぎ、確実に保管するのが検認の目的です。
また、利害関係者に遺言書の存在を知らせます。
検認には数週間から数カ月の時間が掛かるので、遺言書が発見されたら、できるだけ早く「検認の申し立て」を行いましょう。
ただし、検認は遺言書の状況のみを確認する手続きであり、検認を経たからといって、その遺言書が有効とは限りません。
検認の期日が決まると、申立人は遺言書を家庭裁判所に持参し検認を受けます。(他の相続人は任意参加)
遺言書が返却され、相続人が申請すると「検認済証明書」を交付してもらえます。
公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、検認済証明書が添付された遺言書が必要になります。
※遺言書の捏造や変造、破棄や隠匿は法律違反です。行った場合は「相続欠格」となり、相続人の資格を失います。
遺言書があった場合、故人の想いを優先させることになりますが、内容が現状にそぐわなかったりなどあるかもしれません。
その場合、相続人の全員の合意を得られたら、遺言に従う必要はありませんが、もちろん強制的な合意は問題になります。
自筆証書遺言書保管制度を使っている場合
自筆証書遺言書保管制度を使われている場合は、検認作業は必要ありません。
亡くなった方本人が遺言書を提出したと証明されているので、検認の必要が無いのです。
このように今から遺言書を準備される方は自筆証書遺言書保管制度を活用されることをお勧めします。


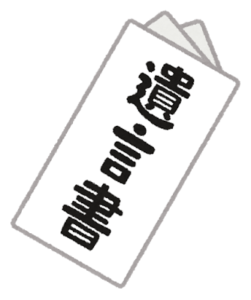







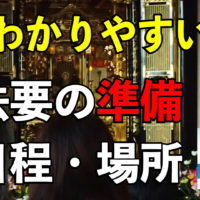







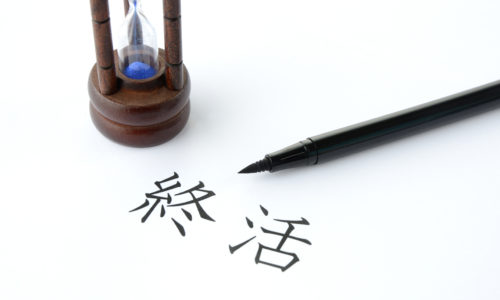

この記事へのコメントはありません。