児童扶養手当とは
よく似ていて知られているものに「児童手当」がありますが、これは児童を育てる保護者に対して支給される手当です。
「児童手当」又は「子ども手当」という名称で15歳の誕生日を迎えた日以降の最初の3月31日までの子の人数に応じて、多くの子供を持つ世帯に支給されます。
それに比べて「児童扶養手当」は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童など、何らかの理由によって、子の養育が困難な状態にある世帯の養育者に対して支給されるものです。
家庭的な事情がある子が受け取れるのが児童扶養手当です。
児童扶養手当の申請について
児童扶養手当の支給を受けるための手続きは、住んでいる市町村の窓口(民生こども課など)で行いますが、注意点としてさかのぼっての支給はありません。
要件に該当したらできる限り早く申請手続きを行ってください。
申請が遅れた場合、もらえたはずのお金がもらえなくなってしまいます。
児童扶養手当の条件
児童扶養手当の条件として、具体的には
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
以上のいずれかに該当する18歳に達する日以降の、最初の3月31日までにある子供(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を保護している人に児童扶養手当が支給されます。
この条件に加え、所得制限もあります。
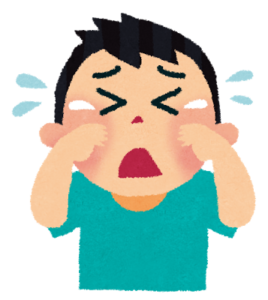
児童扶養手当の所得制限
児童扶養手当は「所得制限」があり、支給額についても「全部支給」と「一部支給」の2種類に分かれています。
そのため、児童扶養手当を受給するには、要件を満たした上で所得制限をクリアししなければなりません。
さらに、所得によって全部支給と一部支給に別れます。
所得は実際の収入金額を基準に判定するものではなく、課税対象とされる金額(給料等の場合は「収入金額から給与所得控除額を控除した金額」)です。
つまり、給料をもらっている方であれば、源泉徴収票の中に記載されている「給与所得控除後の給与所得の金額」が所得制限の判定に使われる金額になります。
| 扶養人数 | 全額支給となる所得制限額 | 一部支給となる所得制限額 |
| 0人 | 49万円 | 192万円 |
| 1人 | 87万円 | 230万円 |
| 2人 | 125万円 | 268万円 |
※なお、3人目以降、1人増えるごとに38万円を所得制限額に加算。
2020.05時点
児童扶養手当の給付金額は?
| 児童の数 | 全額支給 | 一部支給 |
| 児童1人目 | 42,500円 | 10,030円~42,490円 |
| 児童2人目 | 10,040円加算 | 5,020円~10,030円を加算 |
| 児童3人目以降1人につき | 6,020円加算 | 3,010円~6,010円を加算 |
一部支給の場合の計算方法は以下の通りです。
一部支給の限度額-{(所得額-全額支給の所得制限限度額)×0.0226993}
児童扶養手当の差額受給
児童扶養手当制度は、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
基準は以下の通りです。
①お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している。
②父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している。
③母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している。
※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市区町村へご相談ください。
自動扶養手当は受け取れるケースは少ないかもしれませんが、対象の方は確認してみてください。
<葬儀あとのガイドブック参照…P37>









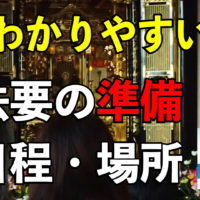




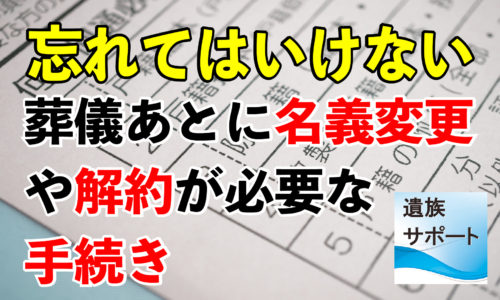

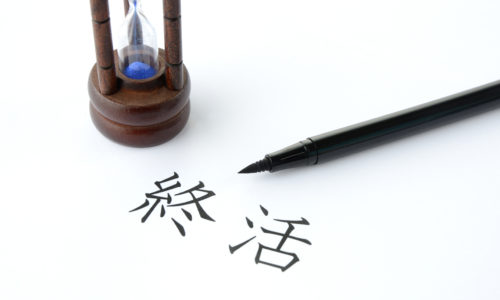


この記事へのコメントはありません。