遺族年金は非課税です
遺族年金は非課税となり、税金はかかりません。
他の所得があったり、ご自身が自分の厚生年金や国民年金ををもらっている場合でも、自分の年金には税金がかかりますが、遺族年金でもらう額は非課税なのです。
所得税・相続税が非課税:遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)
所得税はかかりませんが、相続税がかかるものもあります
所得税が非課税・相続税対象:確定給付企業年金から遺族に支給される年金・特定退職金共済団体が行う退職金共済から遺族に支給される年金
繰り返しになりますが、遺族年金を受け取っている方で働いて収入がある場合、その方の収入の金額に関わらず、遺族年金は非課税です。
所得税の課税対象となるのは遺族年金以外の所得のみです。
遺族年金は非課税なので、確定申告などの申告をする必要がありません。
合わせて検討したい他の家族の「扶養親族」に
遺族年金を受け取っている人でも、他の家族(親族)の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることができます。
ご主人が亡くなって、子供の扶養に入るなどです。
扶養親族になるには年間所得が38万円以内(給与のみなら103万円以下)という条件がありますが、遺族年金はこの所得に含まれません。
遺族年金をいくら受け取っていても、この条件はクリアできます。
他の家族の扶養に入ると、扶養控除によりその家族の所得税や住民税が安くなるため、世帯としてのメリットがあります。
その際、次に紹介する「健康保険のお被扶養者」も検討しましょう。
さらに検討したい他の家族の「健康保険の被扶養者」に
遺族年金を受け取っている方でも、他の家族に生計を維持されている(養ってもらっている)となると、その家族が加入している健康保険や共済組合の被扶養者になることができます。
被扶養者になれば、遺族年金を受けている人は健康保険料を負担せずに良いのです。
ただし、被扶養者になるにも収入要件があり、年間収入(遺族年金も含む)が130万円(60歳以上等は180万円)未満で、健康保険の場合は被保険者の収入の1/2未満でなければなりません。
ただしここで注意が、健康保険や共済組合の場合は、税金の扶養控除と違い、収入要件に遺族年金の額も含むことになります。
また他の家族に生計を維持されていても、その家族が国民健康保険に加入している場合は、被扶養者というメリットはありません。(一人ひとりの保険料で計算されるからです)
他の家族に入るとなったら、同居しなければいけないと思いがちですが、同居は必須ではなく、実態がどうなっているかでの判断基準が大きなポイントとなります。
あくまでも認められたらということですので、必ずしもできることではないと認識してください。


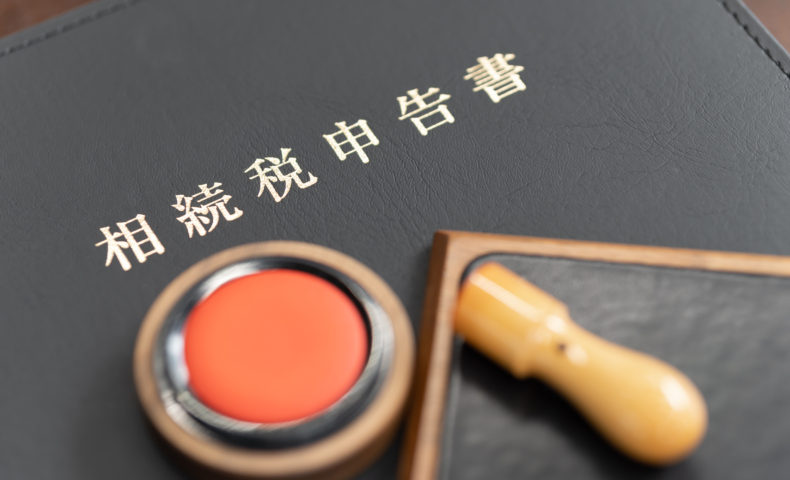







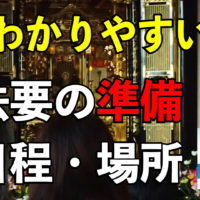






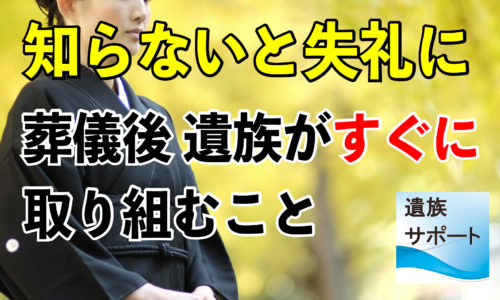
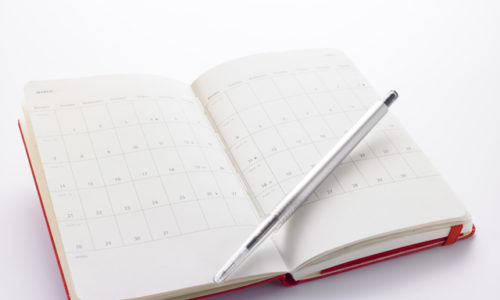
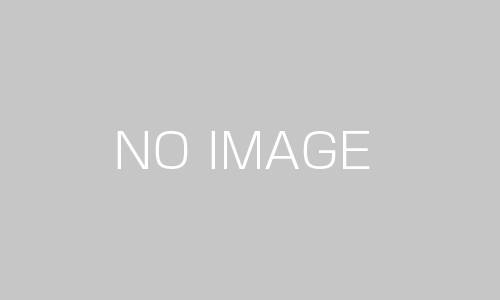
この記事へのコメントはありません。