遺言書が簡単に作成し保管できるようになっています。これは2段階のスケジュールで行われます。
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
遺産の目録はパソコンで作成したり、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付したりすることができ、遺言書が作りやすくなりました。なお、パソコン等で作った目録にも「署名押印」は必要ですし、本文は自書しなければなりません。あくまでも遺言書の本文は自署が必要です。
ここで一つ注意が…2019年1月13日以降に作成された遺言は新方式で大丈夫ですが、それ以前に作成された遺言は新方式では無効です。
遺言書はその人が亡くなってから発見される事が多いのですが、その内容が2019年1月13日以前に書かれており、パソコンで目録が作成してあった場合など無効という事になります。
無効とはいえそこには故人の気持ちが入っていますので、ご遺族で協議してその想いにできるだけ沿った形で相続できるといいのですが…
もし競技がまとまらず、争うということになってしまった場合は、残念ながら遺言書は効力を持ちません。
公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度
(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言が便利になります。
自筆証書遺言を作成したら、その遺言を法務局に保管してもらえるようになるのです。
自筆で遺言書を作成される場合は色々と課題がありました。
遺族が勝手に封を開けて見てしまったり(本来は法務局の検認が必要です)、検認に時間が掛かったり、そもそも遺言書の存在を見つけられなかったり等、一人で作成できる自筆証書遺言は簡単ではありますが、それだけリスクもあったのです。
リスクを考え公正証書遺言を選ぶ方も多い状況でした。(公正証書遺言等の違いは他で書きたいと想います)
法務局で保管されるということは、紛失のおそれがないだけでなく、相続人が、遺言者の死後に法務局で遺言の有無確認をすることが可能になります。相続人等はその遺言書の閲覧を請求することも可能です。(遺言者の生存中は認められません)
また、保管される自筆証書遺言については、検認手続が不要になります。これによって相続人側の負担が大幅に減ることが予想されます。
この保管制度は現在まだ始まっていませんが、その後情報があればご紹介したいと想います。
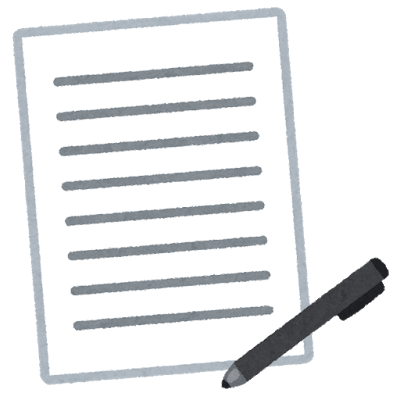
<葬儀あとのガイドブック 関連…P28>









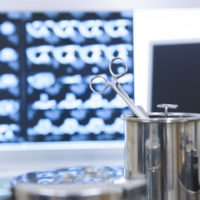
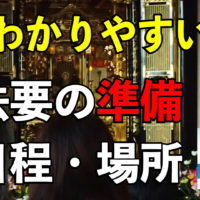






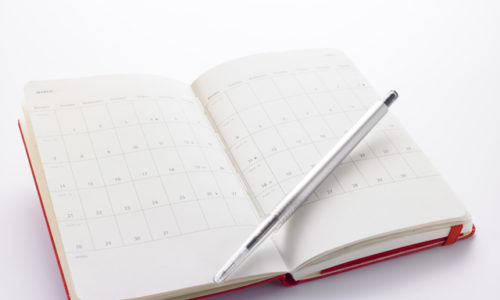


この記事へのコメントはありません。