遺族年金の箇所でも触れていますが、ここでは公的年金受給前の方へ、保険料支払いに関わることをまとめています。
自分(妻)の年金は?
自分自身の年金についてもう一度確認しておきましょう。
年金は、会社員、自営業、専業主婦などで加入する年金が違ってきます。
主なケースで説明しましょう。
亡くなった夫が会社員だった妻
夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、妻自身は国民年金の第3号被保険者になっていたはずです。
要件を満たせば、遺族厚生年金、遺族基礎年金、中高齢寡婦加算を受給できます。
夫が亡くなったあとは、国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きをし(正社員として働き出したら第2号被保険者へ種別変更を行なう)、自分で国民年金の保険料を納めていかなければなりません。
手続きは最寄りの市町村役場か社会保険事務所で行ないます。
手続きをしなかったり、保険料を納めなかったりすると、老齢基礎年金がもらえなくなってしまいます。
亡くなった夫も妻も会社員
夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、要件を満たせば、遺族厚生年金などが受給できます。
ただし、夫の死亡時に、年収が850万円以上あり、それがおおむね5年以上続くとみられる場合には支給されません。
ご自身が会社員で厚生年金に加入していれば、老齢厚生年金を受給する場合、次の三つの選択肢があります。
①「遺族厚生年金」+「老齢基礎年金」
②「ご自身の老齢厚生年金」+「老齢基礎年金」
③「遺族厚生年金」×2/3+「ご自身の老齢厚生年金」×1/2+「老齢基礎年金」
亡くなった夫が自営業だった妻
夫が自営業だった人は、妻自身も国民年金に加入しているはずです。
子供がいる場合は、遺族基礎年金を受給できます。
この遺族基礎年金は、子供が18歳に達した後の3月31日までの支給です。
遺族基礎年金を受給しても、いままでと同様に国民年金の保険料を支払います。
65歳以降に老齢基礎年金が支給されます。
国民年金の保険料が払えない
夫の亡くなった後、生活が苦しく国民年金の保険料が払えない場合は、本人の申請によって保険料が免除される制度があります。
前年度の所得などの要件を満たせば、保険料の半額を免除してくれる「半額免除制度」や全額が免除になる「全額免除制度」を受けられます。
保険料を支払わなければその間は未納期間になってしまいますが、「免除期間」なら、老齢基礎年金の受給権算定の資格期間に入れることができます。
ただし、保険料の額を計算する場合、全額免除については保険料納付済期間の3分の1、半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として計算されます。
保険料の全額または半額を免除された分は、10年間の範囲で保険料を追納することができます。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P64>


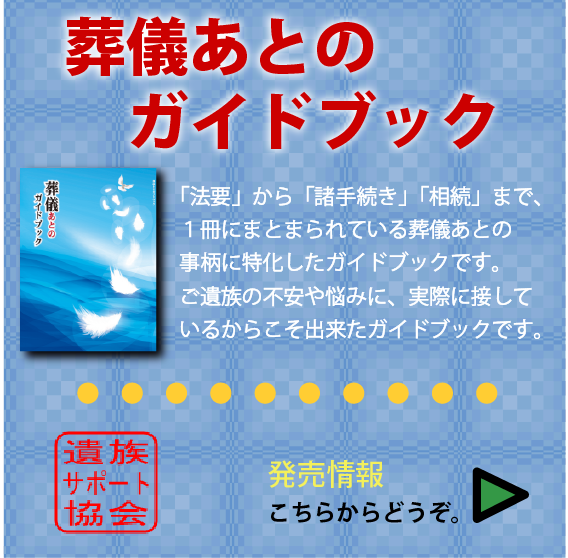
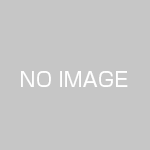






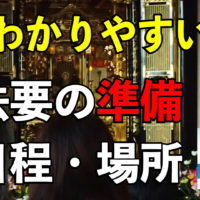




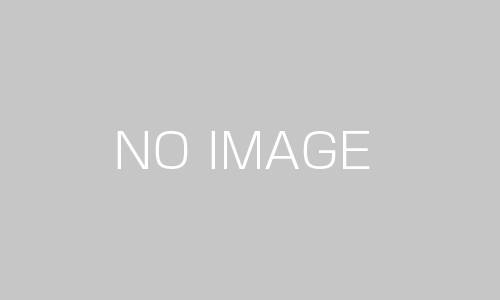




この記事へのコメントはありません。