相続は故人の資産や、権利義務を相続人が引き継ぐことです。
具体的には、預貯金や不動産などのプラスの財産(資産)を引き受ける権利と、事業資金の借り入れやローンなどのマイナスの財産(債務)を引き継ぐ義務です。
プラスとマイナス、どちらの財産もそのまま相続することを「単純承認」といいます。
しかし、故人に大きなマイナス(債務)があった場合、単純承認をしてしまうと相続人はたいへんな事になってしまいます。
そこで相続人の暮らしを守るために2つの選択肢(相続放棄と限定承認)が用意されています。
単純承認とみなされるケース
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もそのまま無条件で受け継ぐことをいいます。
相続の開始を知ってから3か月の間に、何の手続きもしなかった場合、自動的に単純承認したとみなされます。
また、相続放棄や限定承認の手続きの前後に、財産の全部や一部を処分してしまったり、故意に財産を隠していた場合などは、単純承認とみなされます。
例えば亡くなった方が支払っていなかったローンや商品代金を、少額だったので善意で支払ってあげた、などは単純承認したとみなされる行為となりますのでご注意ください。
相続放棄とは
相続人に借金などのマイナス財産の方が多いときには、相続を放棄することができます。
プラスの財産も相続しません。相続を放棄すると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
その人の子がいても代襲相続人とはなりません。
相続放棄をするには、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申し出て「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます。
相続放棄の手続きをしないまま、マイナスの財産が新たにでてきたときには、その債務返済の責任が新たに相続人にかかってきます。
生命保険金に関して、受取人が相続放棄していても、保険金は受取人固有の財産となるため、保険金をもらうことができます。
相続放棄は相続人が複数いても1人で放棄できます。
一度放棄したら取り消しはできません。
※相続の放棄をすると、通常その人に相続税が課税されることはありませんが、生命保険で死亡保険金を受け取っていた場合などは、相続税が課税される場合もあります。
この場合、相続人に対して適用される生命保険金等の非課税枠は使えませんので注意が必要です。
相続放棄の手続きをした場合、放棄した人は初めからいなかったものとみなされるので、代襲相続(相続人の子供が相続すること)もなくなることは前述しましたが、遺産分割協議により取り分ゼロとすることも考えられます。
この場合は相続自体は行なわれたことになりますので、もし債務が後から見つかった場合は、それを相続することになります。
この点が相続放棄との根本的な違いです。
相続をするか、しないか3カ月以内で決めないといけません。
もし3カ月の間に故人の財産調査が終わらなかった場合、3カ月が経過する前に家庭裁判所に「熟慮機関の伸長」を申し立てると、さらに3ヶ月の猶予をもらうことができます。
この他に「限定承認」がありますが、詳しくは別に説明します。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P49>











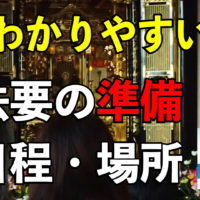




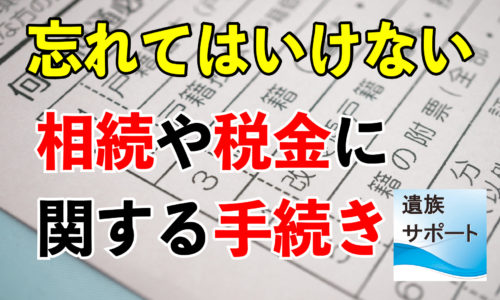




この記事へのコメントはありません。