日本の公的年金制度
日本の公的年金制度は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっている「国民年金」を基礎に、会社員が加入する「厚生年金」(公務員が加入する共済年金は平成27年に統一)での二階建てになっています。
厚生年金の上乗せ部分の企業年金などを含めると三階建てとなります。
被保険者(年金の対象者)は3つに分かれ、第二号被保険者は国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
年金加入者が亡くなって、遺族がどんなものを受給できるかは、年金の種類や故人との続柄、年齢によって変わります。
厚生年金加入者の場合
遺族年金は大きくわけて2つあります。
遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金です。
会社員などの厚生年金加入者が死亡した時、または厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した時、その加入者によって生活基盤を維持されていた遺族に対して支給されるが遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の金額に加算されて支給されます。
またその遺族の範囲も遺族基礎年金より広く「18歳未満の子がいない配偶者」と「その他の人に支給」もプラスされて支給されます。
つまり子がいなくても配偶者に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金部分について
亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。子どものいない妻には支給されません。
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった月の前々月まで、公的年金加入期間の3分の2以上、保険料が納付又は免除されていること。または亡くなった月の前々月までの1年間、保険料の未納がないことが必要です。
亡くなった日から5年以内に手続きをしなければなりません。
遺族厚生(共済)年金部分について
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)
子のある配偶者、又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。
なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
1級・2級の障害厚生年金を受けられる方の場合でも、支給されます。
30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。
遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則として、亡くなった方が生きていた場合に受け取ることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3相当額となります。
手続きは、亡くなった日から5年以内に行わなければなりません。
厚生年金の中高齢寡婦加算
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されません。子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が亡くなったときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
厚生年金の経過的寡婦加算
妻は65歳で妻自身が老齢基礎年金をもらえるので、支給は停止されます。
しかし、昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、国民年金の任意加入期間が足りず、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算額より少なくなります。
これを補うため、65歳となってからも、妻の生年月日に応じ、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が支給されます。
年金関係は様々なルールがあり非常に難しく感じられると思います。
ただ、今後のご遺族の収入になる大きな制度ですので、手続きの中でも早めに終わらせたいものです。
また故人の状況で年金額も変わってくるので、わからないことがあれば手続き先の市区町村役場の窓口、年金事務所または年金相談センターに問い合わせしてみましょう。
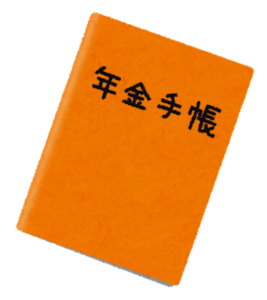
<葬儀あとのガイドブック抜粋…P34>










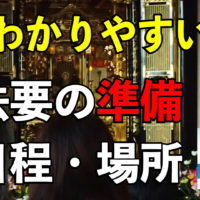









この記事へのコメントはありません。