「忌中(きちゅう)」も「喪中(もちゅう)」も「身内の死に際して身を慎む期間」を指します。
「忌中」とはご家族がお亡くなりになってから、仏式では四十九日、神式では五十日祭、キリスト教は忌明けがありませんが一カ月後の召天記念日までと考えていいでしょう。
忌引きを終えても忌中の期間は死の穢れが強い時期と言われ、祭り事などには出ることを避けたほうがよいといわれています。
また、この忌中には忌服期間(忌引き)があります。
忌服期間(忌引き)とは、明治七年に故人との関係によって忌中と喪中の期間が細かく決められた太政官布告の「服忌令」が出されました。
そんな事まで決められていたんですねぇ。
しかしそれは、百年以上も前のもので、現在では社会と適合した期間に修正されています。
会社勤務の方などで身内が亡くなった際、服務規程などで続柄により数日休んで良いという規定はその名残りでしょう。
この期間は仕事や学校を休み、むやみな外出を控え自宅で故人を弔うことが目的とされています。
四十九日を過ぎたら「忌明け」となります。(忌明け法要は三十五日で行われることもあります)
死を穢れとする考え方からきているもので、精神的なショックを受けている遺族が故人を偲び、時間をかけて精神的な傷を癒す時間とも言えるでしょう。
「喪中」は宗教を問わず一年間とされることが多いようです。
喪中は年賀状は出さず、欠礼をわびるあいさつ状を12月の初めまでに送ります。この間は慶事や祭典を避けるものとされていますが、遺族にとって大事なことであれば「故人もお許しくださる」と柔軟に考えるケースは多いようです。
<関連:葬儀あとのガイドブック P22より>
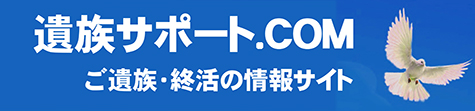



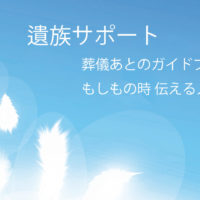






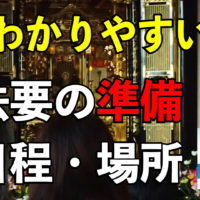








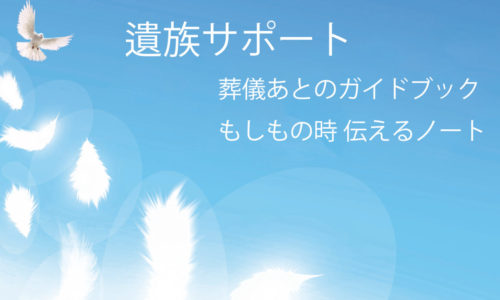
この記事へのコメントはありません。